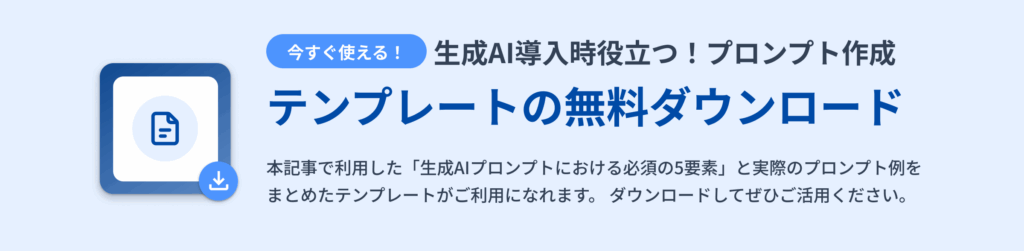第2回:まずは触ってみる、そして深く理解する〜ステップ1・2の実践方法〜
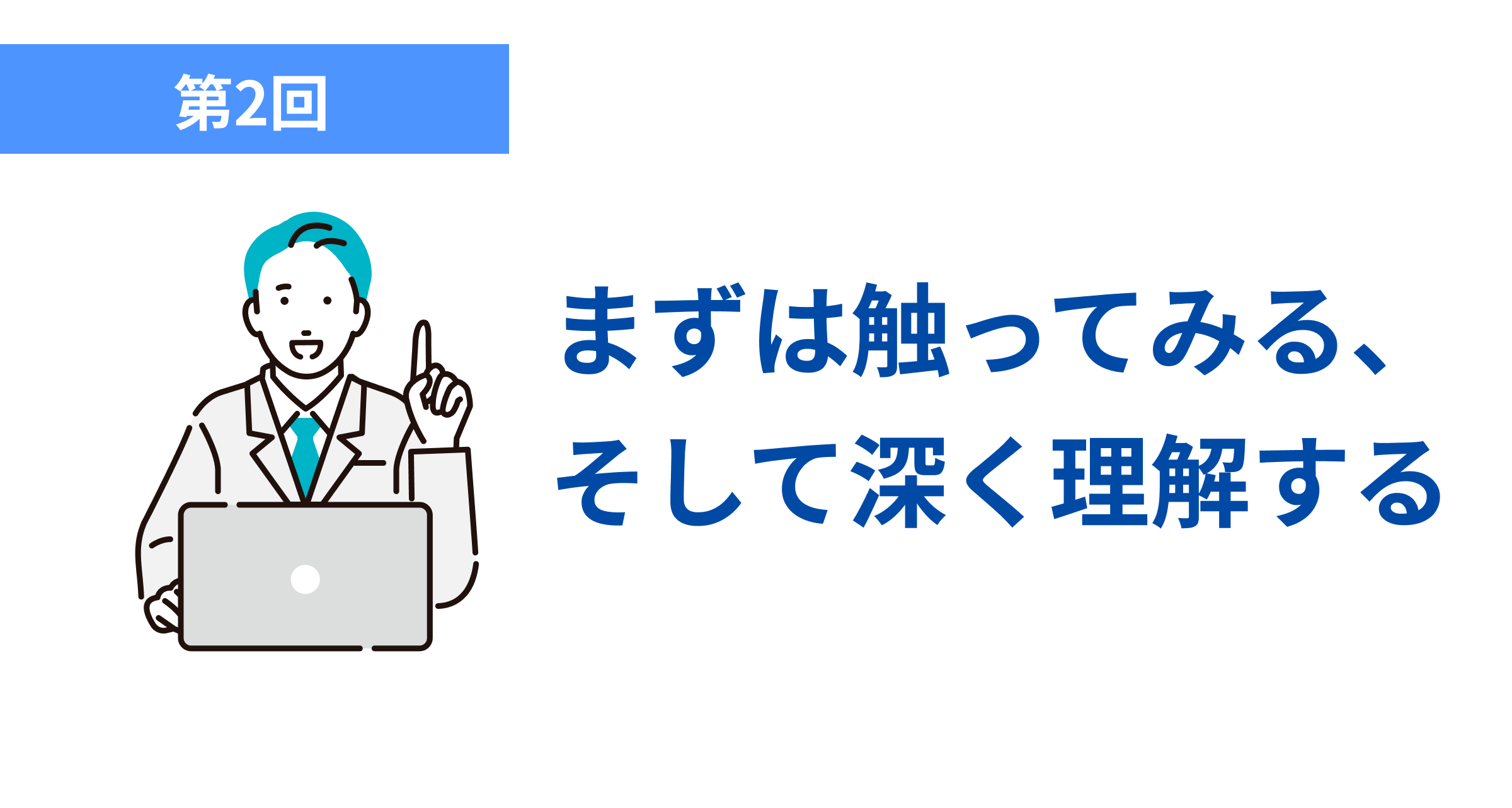
本連載では、私たちPSソリューションズがバックオフィス部門で実践した生成AIの導入プロセスとその具体的な成果、導入時の注意点などについて、5回にわたって詳しくご紹介しています。
前回は、当社が実践した「生成AI浸透の3ステップ」の概要をご紹介しました。今回は、その第1段階である「ステップ1:触れる」と第2段階である「ステップ3:深める」について、具体的な実施内容と参加者の反応を詳しく解説します。記事の最後には無料ダウンロード特典もご用意しています。
ステップ1「触れる」:気軽に生成AIに触れてみる
多くの企業では、生成AIツールを導入しても「使い方がわからない」「何に使えるのかイメージできない」という理由で、結局活用が進まないケースが少なくありません。当社でも、プロジェクト開始前には同様の声が聞かれました。
こうした状況を踏まえ、最初のステップでは「まずは生成AIに慣れてもらうこと」を最優先に据えました。生成AIは自然言語での対話という新しいインターフェースを持つため、ある程度使い続けないと真の効果を実感できません。しかし、いきなり業務での活用を求めると、慣れないうちは思うような結果が得られず、「使えない」「業務に合わない」という印象を持たれてしまう可能性があります。
この問題を解決するため、まずは情報漏えいなどの懸念が一切ないプライベートでの活用を積極的に推奨しました。プライベートでの利用であれば、期待通りの結果が得られなくても業務に影響することはありません。この「失敗しても大丈夫」という安心感の中で、十分に生成AIの特性を理解し、効果的な使い方を身につけてもらうことにしたのです。
具体的な活用例
具体的には週1回30分の勉強会を約2ヵ月にわたって開催し、生成AIの基本的な機能を紹介しながら、次のような使い方を参加者に提案しました。
- 夕飯の献立やレシピのアイデア出し
- イベントの企画や余興のヒント
- 年賀状やクリスマスカードの画像作成
- 子どもの学習サポート
- 英会話の練習相手
これらの活用は、すべて一般的な情報のみを扱うため、社内の情報が漏えいするセキュリティ上の懸念がありません。また、「失敗しても困らない」という安心感の中で、生成AIがどのようなものなのかを体感できます。
ステップ1の実施により、参加者には明確な変化が見られました。プロジェクト開始前は「生成AIは難しそう」ととまどっていた参加者が、「意外と簡単だった」「気軽に試せるツールだった」という認識に変わりました。
夕飯のメニューや年賀状作成で実際に効果を体感した参加者からは、「他にどんなことができるのか試してみたい」「仕事でも使えそう」といった前向きな声が聞かれるようになりました。このような変化により、ステップ2での本格的な学習に向けた土台が築かれ、参加者全員が積極的な姿勢でプロンプト作成の技術習得に取り組めるようになりました。
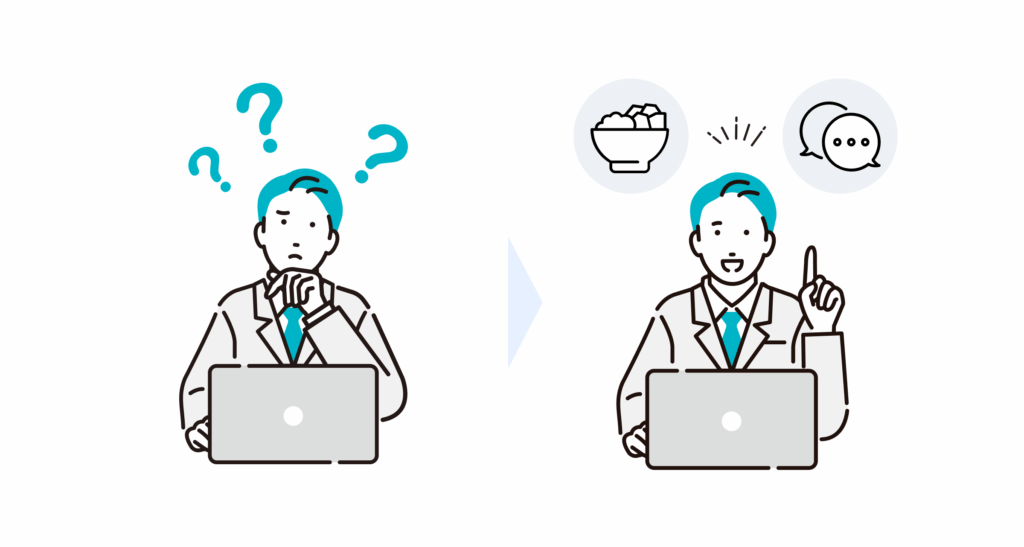
ステップ2「深める」:プロンプトの技術を身につける
引き続き勉強会を開催し、ステップ1で生成AIツールに慣れ親しんだ後は、より効果的な使い方に焦点を移して学んでいきました。ここでポイントとなったのは、効果的なプロンプト(AIへの指示文)の書き方を学ぶことでした。
「Google検索」と「生成AI」の違いを理解する
勉強会を進める中で気づいたのは、一部の参加者が生成AIに対して「マニュアル 作成」といったように、Google検索と同じように単語だけを入力していることでした。しかし、これでは思うような回答が得らません。生成AIは「自然言語での対話を通じて回答を生成するツール」です。キーワードだけでは生成AIは何を求められているのか理解できず、期待とは異なる回答になってしまうのです。
そこで大切なことは、人間に業務依頼するときと同じように、丁寧に説明すること。プロジェクト参加者には「新入社員向けの操作マニュアルを作成してください」と詳細に伝える、「作って」ではなく「作成してください」と明確に依頼するなど、プロンプト(AIへの指示文)の書き方を変えることで、劇的に回答の質が向上することを実感してもらいました。
| Google検索 | 生成AI | |
| 入力方法 | キーワード・単語が中心 | 自然言語(日本語の文章)での会話 |
| 結果の表示 | 関連するWebページのリストを表示 | 一つの回答として情報をまとめて提示 |
| 情報収集 | 複数のサイトを行き来して収集・整理する必要がある | 質問に対して直接的な回答が生成される |
| 検索結果の一貫性 | 同じキーワードであれば、基本的に同じ検索結果が出る | 同じ質問をしても毎回異なる結果が返ってくる |
| 信頼性 | 情報の作成者や発信者がわかりやすく、信頼性の判断がしやすい | 誤った情報(ハルシネーション)が出力されるリスクがあり、情報の真偽確認が必要 |
「5つの要素」で効果的なプロンプト作成
勉強会では、効果的なプロンプト作成のための5つの要素を紹介しました。具体的には次のようなものです。
【5つの要素】
| 観点 | 内容 |
| ① 依頼の背景と目的 | 誰が・何のために出力を求めているのかを明確に伝えると、生成の方向性が大きくブレにくくなります。(例:「新卒研修用の説明資料として使用」「営業担当者向け」など) |
| ② 読み手・書き手の想定 | 誰に向けた出力なのか(読み手)と、どういった立場で書くのか(書き手)を明示することで、トーンや用語選定の精度が上がります。(例:「初心者エンジニア向けに上司が説明」「経営層への報告資料」など) |
| ③ 望ましい出力形式 | 箇条書き、Q&A形式、ストーリー形式など、「どんな見せ方にしたいか」を伝えることで、目的に合った生成が可能になります。 |
| ④ 文体とトーンの指定 | フォーマル、カジュアル、ビジネス調、親しみやすく…など、文体や雰囲気の指定は、実際の使用シーンにフィットする文章を作る鍵です。 |
| ⑤ 参考例やテンプレート | 「こういう形にしてほしい」というサンプルやフォーマットがあると、最短距離で理想の出力が得られます。※完全一致させる必要はなく、方向性のヒントとしてでも有効です。 |
もちろん、すべての項目を毎回埋める必要はありません。依頼内容に応じて必要な要素を選んで使うことで、効率的かつ効果的なプロンプトを作成できます。重要なのは「人間に業務依頼する時と同じように、背景や条件を含めて丁寧に説明する」という考え方です。下記にこの9つの要素を元にしたプロンプトをいくつか挙げました。
●例1:アンケートフォームの作成を依頼するプロンプト
【① 依頼の背景と目的】
社内で生成AI研修を実施したため、効果測定用のアンケートフォームをGoogle Formsで作成します。
【② 読み手・書き手の想定】
あなたは生成AI活用プロジェクトのオーナーとして、研修参加者(バックオフィス部門のメンバー)向けにアンケートを作成してください。
【③ 望ましい出力形式】
全5問(選択式4問、自由記述1問)で構成し、Google Apps Scriptのコードとして出力してください。
【④ 文体とトーンの指定】
親しみやすく、回答しやすい表現を使ってください。
【⑤ 参考例やテンプレート】
「生成AIの理解度」「活用頻度」「満足度」「今後の期待」に関する質問を含めてください。
●例2:企画書の構成案の作成を依頼するプロンプト
【① 依頼の背景と目的】
社内でテレワーク環境改善の提案書を作成し、経営陣から予算確保の承認を得たいと考えています。
【② 読み手・書き手の想定】
あなたは総務担当者として、経営陣に向けて提案を行います。読み手は予算決定権を持つ経営陣です。
【③ 望ましい出力形式】
以下の3つの要素で構成してください:
1.章立て(大見出し・小見出し)
2.各章で記載すべき内容
3.必要な資料・データ
【④ 文体とトーンの指定】
ビジネス文書として適切な、簡潔で論理的な表現を使ってください。
【⑤ 参考例やテンプレート】
現在の課題は「Wi-Fi環境の不安定さ」「集中できる作業環境の不足」「コミュニケーション不足」です。予算上限は300万円で、説得力があり、具体的で実現可能な提案書の構成にしてください。
プロンプト作成のコツ1:「名詞」は的確に
5つの要素を使ってプロンプトを作成する際、特に重要なのが具体的で明確な名詞を使うことです。曖昧な表現ではなく、詳細で明確な名詞を使うことで、生成AIの回答精度は格段に向上します。
【効果的な名詞の例】
- 「マニュアル」ではなく「操作マニュアル」「新人研修マニュアル」
- 「レポート」ではなく「月次売上レポート」「プロジェクト進捗レポート」
- 「提案書」ではなく「新サービス提案書」「コスト削減提案書」
このように、具体的で明確な表現に変えるだけで、生成AIの回答精度は格段に向上します。
プロンプト作成のコツ2:「追加指示」で回答を改善
生成AIが一度の指示で完璧な回答を出力することはまれです。しかし、出力結果に対して以下のように追加指示をすれば、回答内容がブラッシュアップされ、理想的な成果物に近づけられます。
「もう少し詳しく説明してください」
「ビジネス向けのフォーマルな表現に変更してください」
「表形式で整理してください」
「小学生にもわかる言葉で書き直してください」
「文字数を500文字程度に短縮してください」
「予算案を含めた提案書に修正してください」
「メール形式で社内通知文に変更してください」
「A4用紙1枚に収まるよう要点を絞ってください」
Google検索のように一から検索し直す必要がなく、会話を続けながら回答を調整できる点は生成AIの大きなメリットといえます。
ハルシネーションへの理解を深める
勉強会を重ねるうちに、プロジェクト参加者からは「ハルシネーション(AIが事実でない情報を生成すること)が気になる」「どうやって情報の正確性を判断すればよいか」といった質問も出るようになりました。これは、生成AIに慣れてきた証拠でもあります。
ハルシネーションとは、生成AIが学習データにない情報や、事実と異なる内容をもっともらしく生成してしまう現象です。生成AIは「次にくる言葉として最も適切だと判断したもの」を統計的に予測して回答するため、時として事実と異なる内容が生成されます。生成AIの仕組み上、ハルシネーションを完全に避けることは困難と言われています。
プロジェクトでは、この点について正しい理解を促進するとともに、以下のような対策を共有しました。
●複数の情報源で確認する習慣をつける
生成AIの回答をそのまま使用せず、必要に応じて公式サイトや信頼できる資料で事実確認を行う。
●数値や固有名詞は特に注意深くチェックする
統計データ、人名、会社名、法律条文など、正確性が重要な情報は必ず裏取りを行う。
●下書きやアイデア出しとして活用する
完成品ではなく、あくまで「たたき台」として生成AIを活用し、人間が最終的な判断と調整を行う。
この結果、参加者からは「AIは便利だが、すべてを任せるのではなく、最終的な判断は人が行う必要がある」といった適切な理解が生まれました。
勉強会で見えてきた成果
ステップ1からステップ3まで、週1回・2ヵ月弱の勉強会を通じて、参加者には明確な変化が見られました。
- 単語検索から自然言語での対話へと使い方が変化した。
- 「プロンプトの書き方で結果が大きく変わる」ことを実感した。
- 「生成AIとは会話することで正確な答えが得られるツール」という理解が深まった。
- セキュリティや情報の正確性に対する意識も向上した。
特に印象的だったのは、「生成AIって使えるの?」と懐疑的だった参加者が、プロンプトの書き方を学んだ後に「こんなに便利だったんですね」と評価を一変させたことでした。多くの場合、「使えない」と感じる原因は生成AI自体の性能ではなく、効果的な使い方を知らないことにあります。
当プロジェクトでは、いきなり業務での活用を求めるのではなく、まずは「触れる」そして「深める」という段階的アプローチにより、参加者に安心して生成AIの学習を進めてもらえました。利用者のレベルに合わせたステップを設計し、無理のないペースで進めることは大切です。
次回は、いよいよ実業務への活用を図るステップ3「変える」について、具体的な事例とその驚くべき効果を詳しくご紹介します。